春が終わる少し前、彼は藍色のシャツを着ていた。
それがやけに似合っていて、私はそれを見るたび、胸の奥を指で撫でられるような痛みを感じた。
「好きだよ」と言われた夜、私は何も返せなかった。
返したら、たぶん壊れる。
そんな確信だけがあった。
私たちは恋人ではなかった。
でも友達とも違った。
手を繋いだこともないのに、心だけがどうしようもなく絡まっていた。
会えば笑い合い、離れれば考えすぎて眠れなくなる。
それが恋だと、あの頃の私は思い込んでいた。
ある日、彼が言った。
「俺たちって、何なんだろうな」
その一言で、私の中の何かがほどけた。
ほどけた糸は二度と同じ形には戻らない。
分かっていたのに、まだ掴んでいたかった。
彼の青いシャツの袖口には、小さなボタンがついていた。
深い藍色の中に金の糸が走るような、歪んだ模様。
私はそのボタンを見つめながら思った。
きっと私たちの関係も、あんなふうに綺麗な歪さで繋がっていたのだと。
季節が変わる。
彼は転勤で街を離れた。
送別の夜、私は最後に「好きだった」とだけ言った。
彼は何も言わずに笑って、グラスの底で氷を転がした。
藍色の空に、春の残り香が薄く滲んでいた。
痛みは静かに沈んでいく。
それでもあの青が、今も胸のどこかで、光を失わずにいる。
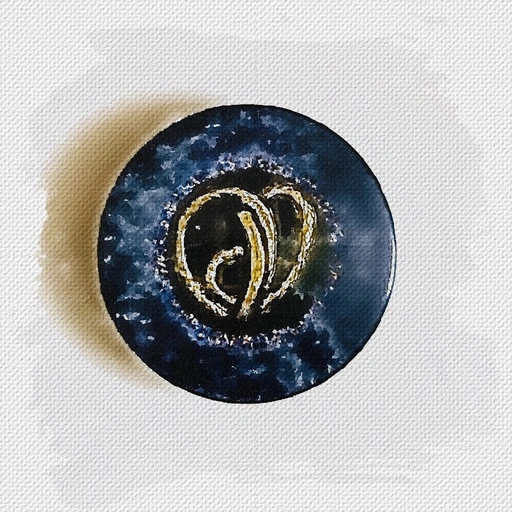


コメント